命を救うための応急手当
2021年2月号
今月のクイズ
交通事故で倒れている人を目の前にしたとき、あなたは助けるために、適切に動くことができますか?「助けたい」と思っても応急手当の知識が無ければ、事故の光景にひるんでしまい行動をとれないかもしれません。
今月は、救急隊が到着するまでに行う応急手当の重要性を理解するとともに、感染症等に配慮した応急手当の方法についてみてみましょう。
事故発生から救急隊に引き継ぐまでの応急手当が、命を救う分かれ目になる!
2017年中に、交通事故で救急隊が病院等に搬送した人数は441,582人でした。そのうち、死亡は1,871人、重傷及び中等傷で入院した人は105,267人です。事故にあった人の約1/4が入院するほどのケガを負っています(図1)。
交通事故が起きたとき、被害状況を把握して119番通報をするまでに数分かかり、通報から救急隊が到着するまではさらに約9分強かかります。ところが、負傷者は心臓が停止してから約3分、呼吸停止になると約10分、多量出血だと約30分で死亡率が50%を超えると言われています。
2017年中の消防庁のデータによると、救急隊が到着するまでに、一般市民によって心肺蘇生が施された心肺機能停止状態(心臓が原因)の傷病者は14,965人でしたが、心肺蘇生されなかったケースに比べると1か月後の生存率は約2倍にもなりました。社会復帰率に至っては、約3倍近くの開きがあります。
また、自動体外式除細動器(AED)を施された傷病者のみに絞ると、1か月後の生存率は55.9%、社会復帰率は48.2%になります。救急隊に引き継ぐまでに、事故当事者や居合わせた人で速やかな応急手当を行えるかどうかが、命を救う分かれ目になります。
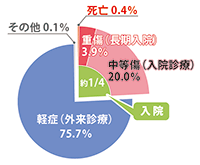
- ※構成比は小数点第2位を四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。
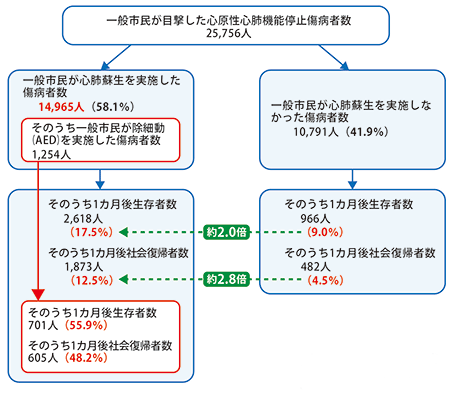
- 図1、2出典:総務省消防庁 令和元年12月「令和元年版救急・救助の現況」より弊社作成
速やかな応急手当を行うためには
新型コロナウイルス等のように飛沫を介する感染症や、肝炎ウイルス等のように血液を介する感染症に気を付けながら、速やかに心肺蘇生などの応急手当を行うためにはどうしたらよいのかをみてみましょう。
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた最新の救急蘇生法については、以下リンクをご覧ください。
応急手当をする前に
119番通報しましょう
 マスクを着用しましょう
マスクを着用しましょう 傷病者の状態を確認するときは、顔を近づけないようにしましょう
傷病者の状態を確認するときは、顔を近づけないようにしましょう

呼吸をしていない場合
心臓マッサージをしましょう
 乾いたハンカチやタオル、マスクなどがあれば、負傷者の鼻と口にかぶせて、飛沫の飛散を防ぎましょう
乾いたハンカチやタオル、マスクなどがあれば、負傷者の鼻と口にかぶせて、飛沫の飛散を防ぎましょう
心臓マッサージは、手の甲にもう一方の手を上からあわせ、胸の真ん中を強く圧迫し、緩めて胸が元の高さまで戻るのを1回として、次の要領で繰り返しましょう。
「強く」(5cm以上位に沈む程度)
「速く」(1分間に約100~120回のテンポ)
「絶え間なく」(連続して) ※成人の場合
AEDを使いましょう
AEDの音声アナウンスの手順に従って処置を行いましょう。
AEDを施しても呼吸が戻らない場合は、心臓マッサージを続けましょう。
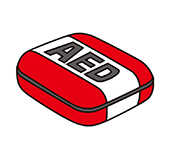
出血がある場合
直ちに止血しましょう
 手が血液に直接触れないように、ゴムやビニールの手袋を装着します。手袋が無い場合は、ビニール袋を代用しましょう
手が血液に直接触れないように、ゴムやビニールの手袋を装着します。手袋が無い場合は、ビニール袋を代用しましょう
意識があっても出血が多い場合は、命の危険があります。出血している箇所を見つけ、できるだけ清潔なハンカチやタオル等を当てて、その上から直接圧迫しましょう。出血が止まらない場合は、出血箇所から外れていたり、圧迫する力が弱かったりすることが考えられます。救急隊に引き継ぐまで、出血箇所をしっかり押さえしょう。
救急隊に引き継いだ後
 速やかに石鹸を使い、流水で手と顔を洗いましょう
速やかに石鹸を使い、流水で手と顔を洗いましょう 応急手当に使った布類や手袋などは、直接触れないように新たなビニール袋に入れ廃棄しましょう
応急手当に使った布類や手袋などは、直接触れないように新たなビニール袋に入れ廃棄しましょう
- 参考:厚生労働省「救急蘇生法の指針 2015(市民用)」、一般財団法人日本救急医療財団「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)」を参考に弊社作成
交通事故の発生から救急隊が到着するまでの数分間が、倒れている人の命を救う分かれ目になります。心肺蘇生や止血などの応急手当ができるようにしましょう。
今月のクイズの答え
-
(3)
64.4%死亡事故は100.8%、重傷事故は84.2%と検挙率が高くなります(検挙件数には、前年以前に認知された事件に係る検挙事件があるため、検挙率が100%を超える場合があります)。交通事故を起こし、被害者を救護せずにその場から立ち去る行為は「犯罪」です。
出典:法務総合研究所 令和2年版「犯罪白書」より

