運転中の焦りやイライラであおり運転をしてしまう?
2021年12月号
今月のクイズ
2020年中に発生した交通事故(309,178件)のうち、12月中の事故件数を次の中から選んでください。
- (1)11,241件(年間の約4%)
- (2)21,241件(年間の約7%)
- (3)31,241件(年間の約10%)
何かと慌ただしくなる年末ですが、つい「急がなきゃ」と焦って運転していませんか?また、交通量の多さにイライラすることはありませんか?
今月は、「焦り」や「イライラ」がつのると「あおり運転」につながる危険性があることをふまえ、常に冷静な運転を行うためには、どうしたらよいのかをみてみましょう。
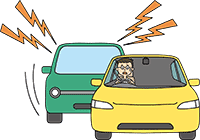
「焦り」や「イライラ」で、自覚が無いままに「あおり運転」をしてしまう?
ドライバーは、「予定の時間に間に合わない」「周囲の車が遅い」など、自分の思い通りに進まないことがあると、「焦り」や「イライラ」を感じます。このような状況が続いたり、重なったりすると、意識が不快な状態に囚われてしまうため周囲への注意が散漫になり、冷静に考え的確な判断を行うことが難しくなります。その結果「先を急ぐ」ことを優先するあまり「あおり運転」に似た運転となり、事故が起きやすい状況をつくってしまいます。
あおり運転による死傷事故の調査をみると、事故当事者(加害者及び被害者)が行ったと考えられる道路交通法違反は、進路変更禁止違反が最も多く、速度超過違反、追越し方法違反、車間距離保持義務違反も多くなっています(図1)。
「時間に追われて焦っている」「色々な状況が重なってイライラする」ときこそ、冷静に交通状況を把握して、事故を防ぐ運転行動をとる必要があります。
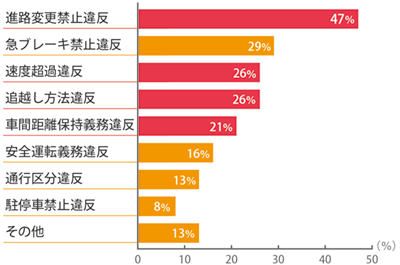
- ※構成比は小数点第1位を四捨五入して表示しているため、合計が200%(100%+100%)にならない場合があります。
- 出典:公益財団法人国際交通安全学会 IATSS Review Vol.43 No.3 2019年2月 警察庁 矢武陽子著「日本におけるあおり運転の事例調査」より弊社作成
事故を起こさなくても「あおり運転」は妨害運転罪が適用される
2020年6月から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うと、図2の通り妨害運転罪が適用されることになりました。
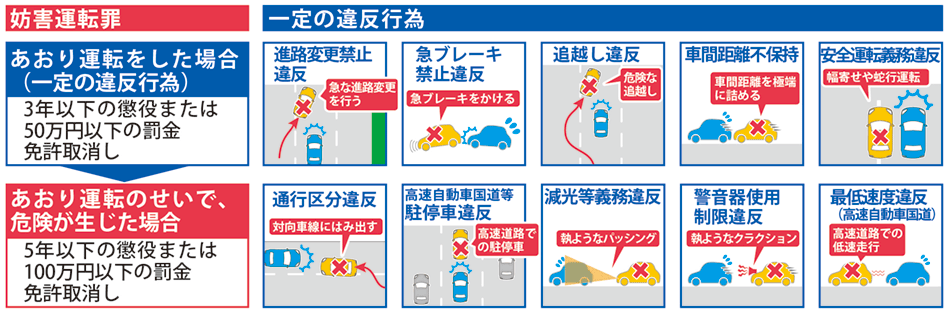
「焦り」や「イライラ」を抑え、冷静な運転を行うためには
「焦り」や「イライラ」がつのると自覚が無いまま「あおり運転」を行い、他車に不安や恐怖を与える可能性があると同時に、他車から悪質な「あおり運転」を受けるきっかけをつくってしまう危険性も潜んでいます。常に冷静な運転を行うためには、どうしたらよいのかをみてみましょう。
運転前の予防策
安全な走行ルートを計画しましょう
時間に余裕をもって出発しましょう
事故が起きやすい交差点を通る場合は…
交差点での事故は多く、2020年中に発生した交通事故のうち約56%*が交差点で起きています。一般社団法人日本損害保険協会が提供している「全国交通事故多発交差点マップ」では、事故が多発している交差点について、その特徴や予防策など安全に通過するためのポイントが記載されています。事故が起きやすい交差点を通過する場合は、参考にしましょう。
- *出典:警察庁交通局 令和3年2月「令和2年中の交通事故の発生状況」より
安全な運転行動
法定速度を守り、十分な車間距離をとって、高速道路では走行車線を走りましょう
急な割り込みをされたとき、車間距離を十分にとっていれば、焦らず安全に対処することができます。十分な車間距離をとりましょう。
また、高速道路で追越し車線を走り続けると、追越しをしたい他車の進路を塞いでしまい、あおり運転を受ける可能性があります。急いでいるときも安全のために、追越しが終わった後は走行車線に戻りましょう。
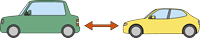
冷静になるために
呼吸を整え、気分を落ち着かせましょう
道路は「自分だけのものではない」と考えましょう
前の車との間を「自分のスペース」と捉えていると、他車が割り込んできたときにムッと腹を立ててしまいます。しかし、「道路は公共のスペースであって、自分だけのものではない」と考えを変えれば、相手に対するストレスが緩和され「お先にどうぞ」と、心にゆとりが生まれます。道路は譲り合い、お互いに気持ちよく走行しましょう。
- 運転前に安全な走行ルートを計画し、時間に余裕をもって出発しましょう。
- 走行時は、法定速度を守り、十分な車間距離をとって、高速道路では走行車線を走りましょう。
- 運転中、他車の行動に「焦り」や「イライラ」を感じたら、呼吸を整えて気分を落ち着かせ、道路は「自分だけのものではない」と考えて、お互いに譲り合い気持ちよく走行しましょう。
今月のクイズの答え
-
(3)
31,241件(年間の約10%)(12月は、1年の中で交通事故が最も多くなります。)
- 出典:公益財団法人交通事故総合分析センター 交通事故統計表データ「都道府県別・発生月別 事故件数」より
- 出典:

