交通事故を起こしたときの対応
2022年12月号
今月のクイズ
2021年中に起きた交通事故は305,196件で、死傷者は364,767人*でした。自分は安全運転なので「事故を起こさない」「事故に巻き込まれない」と思っていても、交通事故はその隙をついて起こることがあり、交通事故は決して他人事ではありません。
今月は、万が一自分が交通事故を起こしたときの対応についてみてみましょう。
- *出典:警察庁交通局 令和4年5月(改訂版)「令和3年中の交通事故の発生状況」より
Step0 冷静になり状況を把握しましょう
事故を起こした直後は、頭が真っ白になりパニックを起こしがちになります。まず、息を大きく吸ってゆっくり吐き、冷静になって周囲の状況を客観的に把握し、正しい判断と落ち着いた行動をとれるようにしましょう。
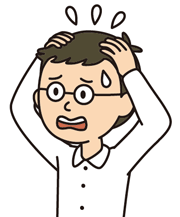
Step1 けが人を救護しましょう
けが人がいないかを確認しましょう。けが人がいる場合は救護が最優先です。被害者の救護をせずにそのまま立ち去ると、ひき逃げ(救護措置義務違反)事件になります(道路交通法72条)。また、けがが軽いと思っても、あとで重症化する可能性がありますので、必ず病院で診察を受けてもらうようにしましょう。とくに、相手が子どもの場合は、大人が「大丈夫?」と問いかけても、事故のショックで「うん」と答えてしまう可能性があるので注意が必要です。
-
1.
救急隊を呼びましょうけが人がいる場合は、その程度にかかわらず119番通報をして救急隊を呼びましょう。
-
2.
応急手当を行いましょう交通事故の発生時は、被害状況を把握して119番通報をするまでに数分かかり、通報から救急隊が到着するまではさらに約9分(全国平均)*1かかります。ところが、負傷者は心臓が停止してから約3分、呼吸停止になると約10分、多量出血だと約30分で死亡率が50%を超えると言われています(これらの関係を曲線で示したものを「カーラーの救命曲線」といいます。)。その間に命を繋げるための応急手当を行いましょう。
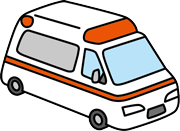
- *1出典:総務省消防庁 報道資料 令和3年12月「令和3年版 救急・救助の現況」の公表より
- 呼吸をしていない場合
- 心臓マッサージをしましょう
- 呼びかけに応じない、呼吸をしていない等が確認されたら、周囲の人に「AEDを探してください」と声をかけ、心臓マッサージを行いましょう。
成人の場合、手の甲にもう一方の手を上からあわせ、
・胸の真ん中を強く圧迫し(5cm以上位に沈む程度)緩めて胸が元の高さまで戻るのを1回とします。
・1分間に約100~120回の速いテンポで繰り返します。 - AEDを使いましょう
- AEDが届いたら、音声アナウンスの手順に従って処置を行いましょう。
AEDを施しても呼吸が戻らない場合は、心臓マッサージを続けましょう。
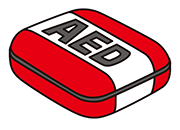
- 出血をしている場合
- 直ちに止血の処置をしましょう
- 意識があっても出血が多い場合は、命の危険があります。出血している箇所を見つけ、できるだけ清潔なハンカチやタオル等を当て、その上から直接圧迫しましょう。出血が止まらない場合は、出血箇所から外れていたり、圧迫する力が弱かったりすることが考えられます。救急隊に引き継ぐまで、出血箇所をしっかり押さえましょう。救急隊に引き継いだ後は、速やかに石鹸を使い、流水で手を洗いましょう。
講習会で応急救護の体験をしてみましょう
応急手当の知識だけでは、万が一のときに思うように動けません。各都道府県の消防本部や病院、日本赤十字社などでは、応急救護の体験をすることができる講習会を開催しています。応急救護の体験は交通事故や災害に遭遇したときに、負傷者へ手を差し伸べる勇気のもとになり、大切な命を救えるチャンスにつながります。お近くの団体のホームページにアクセスし、受講してみましょう。
- 参考:厚生労働省「救急蘇生法の指針 2020(市民用)」を参考に弊社作成
Step2 2次災害の防止・警察等への連絡・連絡先の交換や事故状況の記録を行いましょう
けが人の救護を行った後、事故現場の状況に応じて緊急度の高さは変わりますが、適宜対応すべき事項についてみてみましょう。
交通事故の2次災害を防ぎましょう
事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や2次災害を引き起こす原因になります。
-
1.
ハザードランプを点滅させて、速やかに安全な場所へ移動させましょう
- 2.
二次災害を防ぐために停止表示器材を事故車の後方に置き、後続車に危険を知らせましょう
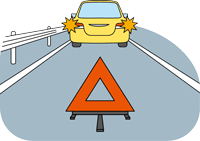
警察へ連絡しましょう
「けが人はいないし、車体をこすっただけだから」とか、「話し合いで何とかなりそうだし、急いでるから」と警察に届け出ないでいると、後になって体調が悪くなったり、事故状況の認識が相手の方と食い違ったりしてトラブルになるおそれがあります。事故現場は、冷静に考えて判断することが難しい状況になるので、どんなに軽微な事故だと思っても必ず警察に届け出て、事故状況の検分を行い「交通事故証明書」をもらいましょう。警察には「だれが」「いつ」「どこで」「どんな状況で」「どうなったか」を、正確に伝えましょう。

警察庁の「110番映像通報システム」の試験運用が始まりました
「110番映像通報システム」は、音声通話だけでは説明が難しい事件・事故等の現場状況を、スマートフォン等を用いて警察に通報することができるシステムです。110番通報時に、警察から映像などの送信が可能か確認された後、通報者のスマートフォン等に送られるショートメッセージ(SMS)の専用URLにアクセスして、撮影映像を送ります。警察や現場に急行する警察官は、映像の共有により的確な状況把握ができ、現場到着時に速やかな対応を行うことが可能になります。2022年10月から全国で試験運用が開始され、2023年4月から運用実施になる予定です。
相手の方の名前や連絡先等を確認しましょう
お互いの免許証などで「名前」「住所」「連絡先」「車のナンバー」などをその場で確認し、メモ等で記録しましょう。相手の方が車の保険に加入されている場合は、「保険会社名」「証券番号」「契約者名」「連絡先」を確認し、メモ等で記録しましょう。
スマートフォン等のカメラ機能を使って免許証等を記録する場合は、相手の許可を必ず得てから撮影しましょう。
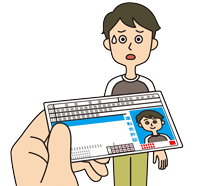
事故状況の記録や、ドライブレコーダーの映像を保存しましょう
目撃者がいれば「名前」「住所」「連絡先」をうかがいメモ等に記録しましょう。
「スピード」「停止位置」「信号」など、その場で確認できることは、スマートフォン等の録音機能やカメラ機能を使って事故状況を記録しましょう。また、ドライブレコーダーを搭載している場合は、事故時の映像を保存しましょう(操作の仕方は取扱説明書で確認しましょう)。事故状況はお互いの責任を決定する上で重要な情報となります。
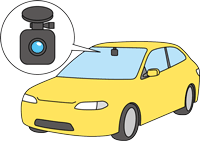
軽微な事故やもらい事故でも、必ず保険会社に連絡しましょう
軽微な事故だったり、自分に過失が無いもらい事故だったりしても、必ず保険会社に連絡しましょう。
また、事故現場では示談などの約束はせずに、保険会社と十分な打ち合わせをしましょう。
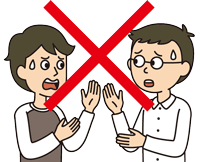
- 事故が起こったら、人命救護が最優先です。冷静になって救急隊【119番】を呼び、応急手当を行いましょう。
- 事故車を安全な場所へ移動して、警察【110番】・保険会社に連絡しましょう。
- その場で確認できることはすべて記録し、相手の方にけがをさせた場合には、誠意をもって対応しましょう。
今月のクイズの答え
-
(3)
366,255件(交通事故による救急搬送人員は342,250人でした。)
- 出典:総務省消防庁 報道資料 令和3年12月「『令和3年版 救急・救助の現況』の公表」より
- 出典:

