高速道路の安全な利用方法
2025年7月号
今月のクイズ
高速道路は一般道路と異なり、交差点や信号機、歩行者等がなく、自動車が安全かつスムーズに移動できることを目的とした自動車専用の道路です。一方で、速度を出しやすい環境のため、事故が起きたときの衝撃は一般道路の何倍も大きく、重大事故となるリスクがあります。今月は、高速道路で発生する代表的な事故やトラブルを知り、安全な利用方法について考えてみましょう。
高速道路で発生する代表的な事故・トラブル
追突事故
高速道路では追突事故が多く発生しており、高速道路で発生した交通事故全体において72%を占めています。また、追突事故のうち、車線停止車への追突が47.5%、走行車への追突が29.1%となっています。高速道路で発生した事故の要因を法令違反別にみると、前方不注意が39.4%、動静不注視が24.1%で、前方や他車の動向への注意不足に起因することがわかります。
- 文中の出典:警察庁「令和6年中の交通事故の発生状況」より
逆走
国土交通省によると、高速道路での逆走事故は高速道路事故全体に比べて、重大事故の割合が約3倍、死亡事故に至っては約38倍となっており、いかに危険であるかがわかります。
高速道路での逆走事案は毎年200件程発生しており、そのうち約2割が死亡・負傷・物損のいずれかの事故に発展しています。また、逆走したドライバーの年齢では65歳以上の高齢者が目立ちますが、約3割は65歳未満のドライバーによるものです。逆走の開始箇所はIC・JCTが最も多く、原因は様々ですが、「過失」が約4割、「故意」が約2割、「認識なし(認知症等)」が約3割となっています。「過失」では、出口への誤進入やIC・JCTでの方向間違いが多く、特に「過失」や「認識なし」の逆走車は左側通行の意識から、追越車線を走行してくる傾向があります。「故意」では、出口を行き過ぎてしまったことで、本線上でUターンするなどして逆走するケースが発生しています。
- 文中の出典:国土交通省 資料「高速道路の逆走発生状況について(2011年~2023年統計)」より
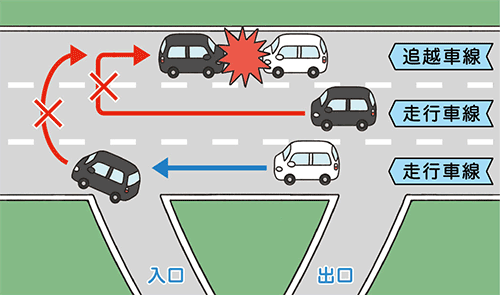
タイヤトラブル・燃料切れ
JAFによると、高速道路におけるロードサービス出動理由では、「タイヤのパンク、バースト、空気圧不足」が42.3%、「燃料切れ」が9.4%となっており、合わせて全体の半数を占めています。特に、一般道路におけるタイヤのトラブルが全体の約20%なのに対し、高速道路ではその2倍以上となっています*1。タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波状の形が現れることがあり、これを「スタンディングウェーブ現象」といいます。この状態が続くとタイヤが加熱し、やがてタイヤのゴムがはがれてしまい、バーストにつながる可能性があります。
- *1出典:JAF「よくあるロードサービス出動理由(2024年度)」より
高速道路走行時の安全ポイント
車間距離の保持と視界の確保
高速道路での事故を防ぐためには、車間距離を保持し、前方の視界を確保することが大切です。先行車両に近い距離で追従していると前方の状況が十分に確認できず、追突や衝突を起こすリスクが高まります。例えば、先行車両が前方の停止車両や逆走車等を避けるために急な進路変更や急ブレーキをした際、後続車が対応できずに停止車両への追突や逆走車との衝突を起こしてしまうケースがあります。特に高速道路での逆走車との遭遇では、発見から衝突まで数秒程度しかない可能性が高く、瞬時に判断・回避をしなければなりません。危険をいち早く発見できるよう、十分な車間距離をとり、常に前方の状況が確認できるようにしておきましょう。
車間距離は100km/hで走行しているときは100m以上、80km/hのときは80m以上といったように、速度をメートルに置き換えた数字分の距離をとるようにします。ただし、雨で路面が濡れていたり、タイヤがすり減っていたりするときは、この倍以上の距離が必要とされています。車間距離は50mごとに設置されている「車間距離確認区間」や「デリネーター」、約20mごとに1セットとなっている「白破線」等で測ることができるので、速度計と併せて確認するように心がけましょう。
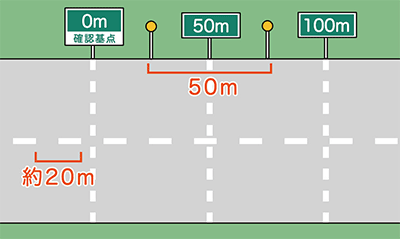
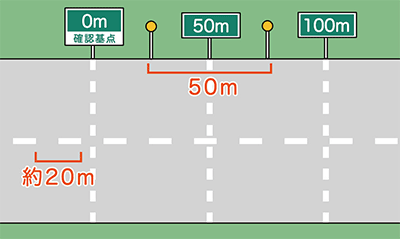
高速道路での事故を防ぐためには、車間距離を保持し、前方の視界を確保することが大切です。先行車両に近い距離で追従していると前方の状況が十分に確認できず、追突や衝突を起こすリスクが高まります。例えば、先行車両が前方の停止車両や逆走車等を避けるために急な進路変更や急ブレーキをした際、後続車が対応できずに停止車両への追突や逆走車との衝突を起こしてしまうケースがあります。特に高速道路での逆走車との遭遇では、発見から衝突まで数秒程度しかない可能性が高く、瞬時に判断・回避をしなければなりません。危険をいち早く発見できるよう、十分な車間距離をとり、常に前方の状況が確認できるようにしておきましょう。
車間距離は100km/hで走行しているときは100m以上、80km/hのときは80m以上といったように、速度をメートルに置き換えた数字分の距離をとるようにします。ただし、雨で路面が濡れていたり、タイヤがすり減っていたりするときは、この倍以上の距離が必要とされています。車間距離は50mごとに設置されている「車間距離確認区間」や「デリネーター」、約20mごとに1セットとなっている「白破線」等で測ることができるので、速度計と併せて確認するように心がけましょう。
こまめな休息
長時間の運転による眠気や疲れ等の影響により、集中力の低下や漫然運転を招くおそれがあります。前方不注意や動静不注視による事故を防ぐためには、こまめな休息が大切です。眠気や疲れをごまかそうと、音楽を大音量で聞いたり、必要以上に同乗者と会話をしたりすることは、かえって気がゆるんだり、注意力が散漫になったりすることがあります。サービスエリアに寄るなどして、早めに休憩をとるようにしましょう。
逆走車との事故防止
逆走車は、自分が逆走していると認識していない場合、追越車線を走行してくる傾向にあるため、走行車線を走ることが逆走車との事故を回避する方法の1つになります。追越車線を走り続けること自体が交通違反*2にもなるため、追い越しを終えたらすぐに走行車線に戻るようにしましょう。万が一目の前に逆走車が現れた場合は、クラクションを鳴らしながら周囲に危険を伝え、衝突するまでの距離・時間の確保と左右の回避空間を確認するために、減速をしましょう。左右の状況を確認しつつ、ハンドル操作で回避するようにします。もし逆走車を見かけたときは同乗者に協力を得るなどして、110番か道路緊急ダイヤル#9910に通報をしましょう。
また、逆走車との遭遇に限らず、自分自身が逆走してしまった場合も甚大なリスクとなります。故意による逆走は絶対にしないでください。目的のICを過ぎてしまった場合でも、次のICで一般レーンに向かい、料金所の係員に申し出ることで、当初の目的地までの通行料金だけで済むことがあります。過失か故意かにかかわらず、もし自身が逆走をしてしまった場合は、慌てず、まずは路肩等の安全な場所で停止し、通報をして指示を仰ぎましょう。
- *2道路交通法第20条
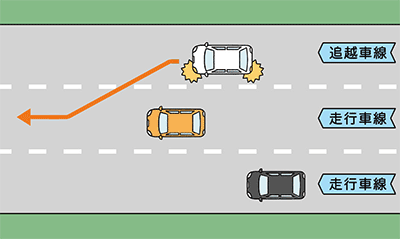
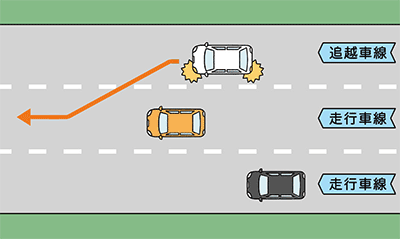
逆走車は、自分が逆走していると認識していない場合、追越車線を走行してくる傾向にあるため、走行車線を走ることが逆走車との事故を回避する方法の1つになります。追越車線を走り続けること自体が交通違反*2にもなるため、追い越しを終えたらすぐに走行車線に戻るようにしましょう。万が一目の前に逆走車が現れた場合は、クラクションを鳴らしながら周囲に危険を伝え、衝突するまでの距離・時間の確保と左右の回避空間を確認するために、減速をしましょう。左右の状況を確認しつつ、ハンドル操作で回避するようにします。もし逆走車を見かけたときは同乗者に協力を得るなどして、110番か道路緊急ダイヤル#9910に通報をしましょう。
また、逆走車との遭遇に限らず、自分自身が逆走してしまった場合も甚大なリスクとなります。故意による逆走は絶対にしないでください。目的のICを過ぎてしまった場合でも、次のICで一般レーンに向かい、料金所の係員に申し出ることで、当初の目的地までの通行料金だけで済むことがあります。過失か故意かにかかわらず、もし自身が逆走をしてしまった場合は、慌てず、まずは路肩等の安全な場所で停止し、通報をして指示を仰ぎましょう。
- *2道路交通法第20条
タイヤの空気圧、燃料、携行品の準備
高速道路でのタイヤトラブルを避けるためには、予め空気圧をやや高めにしておきましょう。高速道路を走行中にガソリンや充電が少なくなると、不安が強くなり、運転に集中できなくなるおそれもあります。長距離の移動になる場合は満タンにしておきましょう。もしもの場合に備え、停止表示器材(三角表示板)や発炎筒を車内に携行しておきます。発炎筒には有効期限がありますので、残りの期限にも注意してください。
今月のクイズの答え
-
(3)
約5割逆走事案では約3割ですが、事故に発展した数では約5割を占めます。
- 出典:国土交通省 資料「高速道路の逆走発生状況について(2011年~2023年統計)」より
- 出典:

