歩行者・自転車等への運転中の配慮
2025年8月号
今月のクイズ
交通の場においては、歩行者・自転車等が安心して利用できるよう配慮することもドライバーの役割となります。今月は、歩行者や自転車、子ども、高齢者、障がいのある人を守るための運転行動について考えてみましょう。
歩行者・自転車等との事故が発生しやすい場所での運転
歩行者・自転車等が万が一事故に遭ってしまった場合には、大きなケガや死亡事故につながってしまうおそれがあります。特に歩道と車道の区別がない道路や横断歩道、交差点、歩道は車との共用部分であるため、ルールを守らなければ事故につながる可能性が高まります。
車道と歩道の区別がない道路
歩行者や自転車のそばを走行するときは、安全な間隔を保ちましょう。安全な間隔がとれないときは、徐行して通過します。なお、2026年5月までには道路交通法が改正され、「自動車が自転車等の右側を通過する際は、間隔に応じた安全な速度で走行しなければならない」という義務が新たに設けられる予定です。
信号機のない横断歩道、自転車横断帯
横断する人がいるときは、必ず一時停止をして安全に横断させましょう。横断が終わるまで待ち、続けて横断しようとする人がいないかを確認してから発進しましょう。横断する人がいるかどうか判断できないときは、いつでも止まれる速度で通行します。
交差点
右左折時は徐行し、安全を確認しながら曲がります。特に左折時の巻き込み事故を起こさないよう、左後方のミラーの死角は必ず目視で確認するようにしましょう。
歩道
歩道を横切って駐車場等に出入りするときは、歩行者がいてもいなくても、歩道の直前で一時停止することが義務付けられています*1。
- *1道路交通法 第17条第2項
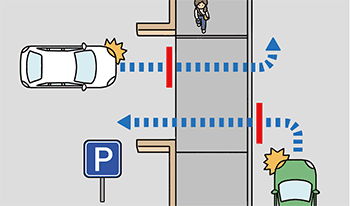
子ども、高齢者、障がいのある人を守るための運転行動
車を運転するドライバーは歩行者の中でも子ども、高齢者、障がいのある人のそばを通るときには、より一層の注意をしなければなりません。
子ども、通学・通園バス
子どもは急な飛び出しや衝動的な行動をとることがあり、おもわぬ事故につながるおそれがあります。
子どもを守るための運転行動
近くに保護者等がおらず、子どもが単独で歩いているときは、一時停止か徐行をして安全に通行させなければなりません。また、児童・園児が乗り降りするために停止している通学・通園バスのそばを通過するときは、徐行しなければなりません。降車後にバスの前後を横断することがないか、子どもの動きに注意しながら進みましょう。
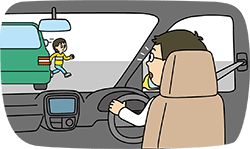
高齢者、車椅子
高齢者や車椅子を利用している人は横断に時間がかかることがあります。信号が変わっても横断しきれず、取り残されてしまうことがあるかもしれません。また、高齢者は視力低下や視野狭窄で車が見えていなかったり、横断歩道以外でも横断したりすることがあります*2。
高齢者や車椅子利用者を守るための運転行動
先頭で信号待ちをしたときは、青信号になってもすぐに発進せず、横断を終えていない人がいないか確認をしましょう。高齢歩行者の死亡事故は、薄暮・夜間に多発しています*3。早めのライト点灯を心がけましょう。
- *2出典:警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」より
- *3出典:交通事故総合分析センター
「性別 年齢学齢別・時間帯別 死者・負傷者数(自転車・歩行者)」より
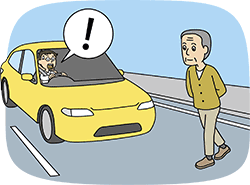
視覚障がいや聴覚障がいがある人
視覚障がいがある人は白杖を持っていたり盲導犬を連れていたりします。音で周囲の状況を把握していますが、雨音・騒音がするところやエンジン音の小さな車では、接近に気づかないことがあります。聴覚障がいがある人も同様に、音では車の接近を感じ取ることができないため、急な横断などをする可能性があります。
視覚障がいがある人を守るための運転行動
視覚障がいがある人のそばを走行するときは、一時停止か徐行をして、その通行を妨げないようにしなければなりません。もしかしたら自車の存在に気がついていないかもしれない、と考えるようにしましょう。視覚障がいがある人に道をゆずるときは直接声をかけて知らせるなど、思いやりを持った行動を心がけましょう。
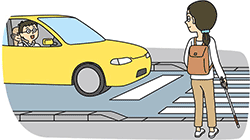
- 歩行者や自転車等との事故が発生しやすい場所では、状況に応じて徐行や一時停止をし、交通ルールを確実に守りましょう
- 子ども・高齢者・障がい者のそばを通るときは、安全に道路を利用できるよう配慮し、思いやりのある運転を心がけましょう
今月のクイズの答え
-
(1)
69.4%937人中、650人が高齢者でした。
- 出典:警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」より
- 出典:

