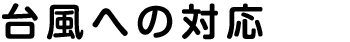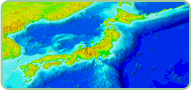台風発生!そのときどうする?
実際に台風が発生したときにどうすればよいか。ポイントとなるのは、素早く正確な情報を収集し、あわてず落ち着いた行動を取ること。過去の事例などから、危険を察知することで被害を避けることができます。
STEP1 防災情報の取得
大雨による災害に巻き込まれないようにするためには、ラジオやテレビ、気象庁のホームページで発表される、防災気象情報を有効に活用することが必要です。
避難が必要な場合には、ケーブルテレビやラジオ、携帯電話へのメールや防災無線などを通じて情報が発せられることもあります。
警戒レベル
各地に甚大な被害をもたらした平成30年豪雨において、気象庁から注意報、警報、市町村からは避難勧告、避難指示(緊急)など様々な情報が住民に対して発信されました。しかし、これらの情報が住民側で正しく理解されていたかなど、様々な課題が残りました。この事態を受けて国は水災、土砂災害について、直感的に住民が危険度と取るべき方法を知ることができるように、市町村が出す「避難情報」と国や都道府県が出す「防災気象情報」を「警戒レベル」として5段階に整理しました。さらに、2021年5月20日からは「避難勧告」を廃止し、警戒レベル4「避難指示」で全員必ず避難することを明確に示しています。
自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。
一方で、多くの場合、防災気象情報は自治体が発令する避難指示等よりも先に発表されます。このため、危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4や高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、避難指示等が発令されていなくてもキキクル(危険度分布)や河川の水位情報等を用いて自ら避難の判断をしてください。
キキクルとは
「キキクル」は、大雨や洪水による災害の危険が、どこで、どのレベルで迫っているかを、地図上で視覚的に知ることができる情報で、気象庁のホームページで公開されています。
テレビやラジオなどの気象情報で注意報や警報が発表されるなど、大雨による災害が発生するおそれのあるときや、急に激しい雨が降ったときは、このページにアクセスし、最新の情報を入手しましょう。大雨による土砂災害の危険度は「土砂キキクル」、短時間の強雨による浸水害の危険度は「浸水キキクル」、河川の洪水災害の危険度は「洪水キキクル」で、確認することができます。
「避難情報」と「防災気象情報」の違い
| 情報の種類 | 発信元 | 発信内容 | 情報発信先 | 情報の 位置付け |
|---|---|---|---|---|
| 防災気象情報 | 国・都道府県 | 気象庁(気象台)や国土交通省(河川事務所など)、都道府県の砂防・河川部局などから発表される情報。 気象、河川、土砂災害などの現象について、災害の発生する危険性が高まってきていることを段階的に知らしめるため、警報、土砂災害警戒情報、(河川の)氾濫危険情報など、各種の情報が発表されることになっている。 |
基本的には市区町村単位や河川ごとのやや広めの情報で発表され、特定の地区(〇丁目や●●学区など)まで絞り込んで発表されるものではない(「危険度分布」は除く)。 | 「警戒レベル相当情報」の位置づけになる。住民が自主的に避難行動をとるための「参考情報」。 |
「防災気象情報」をもとに、自治体の防災担当局部では実際にどの地区において災害の危険性が差し迫っているのかを判断し、地形などを考慮して「避難情報」を発表する。
| 情報の種類 | 発信元 | 発信内容 | 情報発信先 | 情報の 位置付け |
|---|---|---|---|---|
| 避難情報 | 市町村 | 高齢者等避難や避難指示など、住民に災害の危険性を周知し避難行動を促す情報。 気象の状況、それぞれの地域の地形などさまざまな情報を総合している。 |
「市内全域」という形で出される場合もあるが、「〇〇市××町△△2丁目」や「〇〇市××町□□学区」など、地域の実際の状況を考慮し、危険が高まっている地域を絞り込んで発表される場合が多い。 | 警戒レベルそのものを明記し、それぞれの情報や行うべき行動と連動させている。 |
警戒レベル
![避難情報等/気象庁等の情報[警戒レベル]警戒レベル5 [状況]災害発生又は切迫 [避難行動等]警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。緊急安全確保の発令を待ってはいけません。 [避難情報等]緊急安全確保*1 *1市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。 〔市区町村が発令〕 [防災レベル相当情報(例)]大雨特別警報 氾濫発生情報 キキクル(危険度分布)「災害切迫」(黒)等 警戒レベル4までに必ず避難 [警戒レベル]警戒レベル4 [状況]災害のおそれ高い [避難行動等]危険な場所から全員避難しましょう。公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、安全な親戚・知人宅、安全なホテル・旅館、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。 [避難情報等]避難指示 〔市区町村が発令〕 [防災レベル相当情報(例)]土砂災害警戒情報 氾濫危険情報 キキクル(危険度分布)「危険」(紫)等 [警戒レベル]警戒レベル3 [状況]災害のおそれあり [避難行動等]避難に時間を要する人(ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は避難をしましょう。その他の人は、避難の準備を整えましょう。 [避難情報等]高齢者等避難*2 *2警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。 〔市区町村が発令〕 [防災レベル相当情報(例)]大雨警報(土砂災害) 洪水警報 氾濫警戒情報 キキクル(危険度分布)「警戒」(赤)等 [警戒レベル]警戒レベル2 [状況]気象状況悪化 [避難行動等]避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。 [避難情報等]洪水注意報 大雨注意報 等〔気象庁が発表〕 [防災レベル相当情報(例)]氾濫注意情報 キキクル(危険度分布)「注意」(黄)等 [警戒レベル]警戒レベル1 [状況]今後気象状況悪化のおそれ [避難行動等]災害への心構えを高めましょう。 [避難情報等]早期注意報等 〔気象庁が発表〕](/world/egao/taio/typhoon/img/measures_img_01.png)
- ※各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
防災気象情報と警戒レベルとの対応について(気象庁ホームページ)、避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)(内閣府ホームページ)、より弊社作成
土砂災害が起きる前兆現象
大雨警報を発表された場合には、その後の情報に気をつけてください。気象台と都道府県が共同で発表する土砂災害警戒情報が発表された場合には、ただちに避難しましょう。土砂災害警戒情報が出ていなくても、次のような現象が見られた場合はすぐに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、自治体や警察、消防などに通報するようにしましょう。
(前兆現象例)
- 山鳴りがする
- 川の流れがにごり、流木が混ざりはじめる
- 雨が降り続いているのに、川の水位が下がる
- がけや斜面から小石がパラパラと落ちてくる
- 沢や井戸の水がにごる
- 地面にひび割れができる
- 斜面から水が噴き出す
STEP2 危険な場所から離れる・近づかない
台風などで強風や降雨量が増えることが予想される場合は、できるだけ外出を避けましょう。しかし、外出しているときに強風・大雨に遭遇してしまうこともあります。その場合、危険な場所にいるならただちに離れる、危険な場所には近づかないことが大切です。
地下は避ける

強い雨が降り続けると、地面にしみ込まなかった雨水が、低いところに一気に流れ込みます。都市部では、地下街や地下鉄の駅、地下室や地下のガレージなどに流れ込んでいく可能性があります。浸水すると水圧でドアが開かなくなる可能性もあるので、注意が必要です。
川から離れる

大雨が降ると、急に川の水かさが増えます。上流にあるダムで放流が行われると、驚くほどの速さで増水することもあります。避難を呼びかけるサイレンが鳴らなくても、危険を感じたら素早く川辺から離れるようにしましょう。
- ※川の水位の情報は、ホームページや自治体のメールサービスで確認することもできます。
がけ

土砂災害は前触れなく発生することが多いため、雨が長時間にわたって降り続いた場合には、土砂災害危険箇所に指定されている場所はもちろん、危険ながけには近寄らないようにしましょう。
冠水した道路

道路が冠水すると、道路との境目が見えなくなり、側溝などに落下してしまう可能性があります。また、水圧によってふたが開いてしまったマンホールに転落する可能性もあるので、必要以上に歩き回ることは避けた方がよいでしょう。
家族で話し合おう

雨は日常的なものですが、長雨になったり、激しくなったりすることで、思わぬ被害が発生します。市町村が公表しているハザードマップを基に、自宅や学校、職場など、普段の行動範囲の中で、水害や土砂災害などの可能性がある箇所について、家族で話し合っておきましょう。
天気が良い日などに散歩をしながら、家族で状況を確認し、いざというときの避難意識を高めましょう。
関連リンク
![]()
このサイトの情報は一例です。
あなたにとっての防災・減災を考えるきっかけとしてぜひご活用ください!