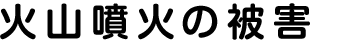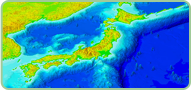火山噴火によって起きる被害
火山が噴火すると、小さな石や巨大な岩石、溶岩や灰、ガスなど、さまざまなものを噴き出します。総じて火山噴出物と呼ばれるこれらの物質は、建物や人に害を及ぼします。どのような現象が発生し、どのような害をもたらすのか、紹介していきます。
噴石

大きさが直径2mm以上の岩石片(火山れき、火山岩塊)を噴石といいます。中でも概ね20~30cm以上のものは「大きな噴石」、火口付近で2mm以上50cm以下、降灰予報で大きさ1cm以上のものは「小さな噴石」と定義されています。大きな噴石は火口から2~4km先まで飛ぶこともあり、風に流されると10km以上離れた地点に落下することも。建物を破壊し、人を殺傷する恐れがあります。
火山灰

直径2mm以下の噴石は、火山灰と定義されます。火山灰は、火口から数十km~数百km先の地点まで飛散し、広域に降下・堆積します。火山灰を吸い込むと、せきや息苦しさ、のどが痛くなるなどの症状が出てきます。数mm積もっただけで、自動車のスリップ事故が発生しやすくなり、鉄道・航空などの交通網も麻痺します。また、農作物の被害、家屋倒壊など、社会生活に深刻な影響を及ぼします。
溶岩流
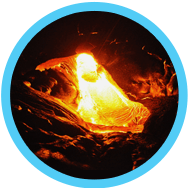
溶けた岩石が地表を流れ下る現象を溶岩流といいます。その温度は高温で、通過したエリアに火災を引き起こすだけではなく、鉄筋の建物さえも破壊します。流下速度は地形や溶岩の温度・組成により異なりますが、比較的ゆっくり流れるので歩行による避難が可能な場合もあります。
火砕流

数百度の非常に高温な溶岩片、火山灰、火山ガスなどが、斜面を急速に流れる現象のことを火砕流といいます。その速度は時速数十kmから数百kmを超え、通過したエリアを焼失、埋没させるなど、大きな破壊力を持っています。火砕流から身を守ることは、非常に困難とされています。
火山泥流・融雪型火山泥流

火山泥流とは、噴出された岩石や火山灰が堆積しているところに大雨が降り、周辺の土砂や岩石を巻き込みながら、高速で流れ下りる現象のことです。また、積雪がある冬季に火山が噴火した場合、熱によって雪が水になり火山泥流が発生します。この現象を融雪型火山泥流といいます。その速度は時速数十kmに達することがあり、広範囲の建物、道路、農耕地を破壊するなど、大規模な災害を引き起こします。
火山ガス

火山の近くでは、マグマに溶けていた二酸化炭素、二酸化硫黄、硫化水素などのさまざまな成分が、ガス(気体)となって地表に噴出されます。噴火がなくてもガスだけが放出される可能性があり、過去にガス中毒による死者も出ています。空気より重いため、谷筋や窪地に溜まりやすいので注意しましょう。
2014年御嶽山噴火

2014年9月27日、長野県と岐阜県の県境にある御嶽山が噴火しました。2015年11月6日現在の消防庁の資料によると、この噴火による死者は58人、行方不明者5人。日本における戦後最悪の火山災害となりました。
噴出物量は50万トン、飛散した大きな噴石も火口から1.5kmの範囲内に収まるなど、爆発力は大きくありませんでした。しかし、近年の登山人気もあり、噴火の現場近くに多くの人がいたことで、被害が大きくなったと考えられています。
消防庁ホームページより弊社作成
口永良部島(新岳)噴火

(出典:海上保安庁)
2015年5月29日午前9時59分、新岳(標高626メートル)で爆発的噴火が発生し、噴煙が高さ9,000m以上まであがり、火砕流が海まで流れました。屋久島町は避難指示を出し、住民ら137人は約12km離れた屋久島に全員避難しました。気象庁は噴火警戒レベルを3(入山規制)から5(避難)に引きあげ、避難指示は同年12月末に一部地域を除いて解除、翌2016年10月に全島で解除されました。
小笠原の海底火山(福徳岡ノ場)噴火

沖縄県国頭村伊部海岸
(2021年10月19日)
(出典:産総研地質調査総合センター)
東京都の中心部から南方に約1,000km以上離れた小笠原諸島。その付近の海底にある火山「福徳岡ノ場」が2021年8月13日に噴火しました。噴煙の高さは約1万6,000mにも及び、この噴火で発生した多量の軽石は海流にのり、約2ヶ月かけて1,300kmほど離れた南西諸島に漂着し始めました。これらの軽石により、漁船やフェリーが出港できない、また、生簀(いけす)で魚が餌と間違って飲み込み大量死するなど、漁業や観光業に影響を及ぼしました。
関連リンク
![]()
このサイトの情報は一例です。
あなたにとっての防災・減災を考えるきっかけとしてぜひご活用ください!