火災保険の現地調査について 現地調査の方法や注意点とは
- 住まい
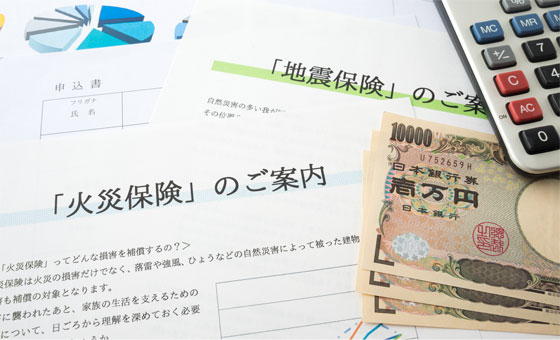
台風や大雨などの自然災害で建物や家財が被害に遭った際、あなたの助けとなるのが火災保険です。補償範囲が火災だけではない事実を知り、いざ申請しようと思っても、自分で申請するのは難しいのでは?と戸惑うこともあるでしょう。
「こんな被害でも大丈夫なのだろうか?」
「必要な書類はどうすればいいの?」
なんて質問をよく耳にします。
「最近よくネットで見かける専門業者に依頼すればいいのかな?」
いえいえ、それは違います。
火災保険の申請は、決して難しいものではありません。
ここでは、自然災害発生から保険申請(請求)から保険金の受け取りまでの流れに沿って、代表例である住宅の台風被害(風災)を例に挙げて詳しく解説します。
1.火災保険の現地調査とは
保険金請求を行うと保険会社から現地調査をしたいと連絡が入ることがあります。わざわざ調査に来るなんて申請内容に問題があったのだろうか、と不安になる契約者も多いでしょう。ここでは現地調査に至るまでの流れと手法について解説します。
(1)現地調査になるまでの流れ
どうして現地調査が必要なのか?
保険金の請求には損害箇所の写真と修理見積書をご提出いただくことになりますが、一例として以下のようなケースでは現地調査が必要になることがあります。
「写真からは損害の範囲や程度の確認が難しいケース」
「見積書に記載された修理内容や範囲などの妥当性の確認が難しいケース」
上記のようなケースにおいて、「損害保険登録鑑定人」といった専門の資格を有した鑑定人などによる現地訪問を踏まえた調査を実施することがあります。
損害保険登録鑑定人とは、建物や動産の保険価額(価値)の算出、損害額の鑑定、事故の原因・状況調査などを行う専門家です。
写真から損害状況が十分に確認できるケースや、見積書の修理内容や範囲などの妥当性が書面で確認できるケースなどは、鑑定人が派遣されないこともあるため、現地調査の実施についてはケースバイケースとなります。
(2)現地調査の主な手法
目視や高所カメラなどを活用した確認
調査の手法は目視や高所カメラなどを活用した確認や、事故状況のヒアリングなどが中心となります。専門業者を伴なって屋根に登るケースもありますが、屋根に登るのは専門業者です。
一般的な広さの建物の場合、調査に要する時間はおよそ一時間程と考えておくといいでしょう。
2.火災保険の現地調査の流れ

ここでは、あなたの自宅を担当する鑑定人や調査員が現地調査に来てから帰るまでと、その後の認定結果の通知までについて時系列で解説します。
(1)調査担当者(保険会社・鑑定人等の訪問)
まずは訪問日程の調整をするため、保険会社の担当者や鑑定人から契約者など訪問する際の窓口となる方とのスケジュール調整がなされ、約束した日時に鑑定人が訪問します。
鑑定人は事故の原因や損害の状況や程度を確認するためにお伺いします。
(2)現地調査内容の説明
火災保険の基本をしっかり確認しよう
現地調査において不明点や質問などがあれば確認するようにしましょう。
(3)屋根・外壁の調査
建物外側の被害の確認が大事な理由
台風などによる風災の場合、雨漏りなどの建物内部に被害があったとしても調査の上で重要となるのは建物外側の被害です。瓦が割れたり乱れたりしていないか、雨樋が壊れていないか等、普段はあまり目にしない部分ですが、風災による損害が無いか調べます。
例えば、雨漏りを風災による損害として認定するためには、風災による建物外側の被害があることが火災保険で補償の対象となる前提となります。つまり、建物の外側が風災によって破損していないと、雨漏りによる損害は補償の対象とはならないのです。
(4)室内・内装の調査
建物外側の風災による破損のない雨漏りは対象外
現地調査では天井や壁などに雨染みなどがないか、雨水はどこから侵入してきたのか等を確認します。
(5)現地調査結果の説明
現地調査が完了すると鑑定人等から今後の対応等について概要の説明があります。基本的には調査した内容を持ち帰って保険会社に報告するため、追って保険会社から結果のご連絡があることをお伝えすることになります。
(6)認定結果の通知
調査が終わってしばらくすると認定結果の連絡があり、内容について合意すると保険金の支払いに関するフェーズになります。この合意を「協定」と言います。
3.火災保険の現地調査での注意点とは
ここからは、被害があるのに保険対象とならない経年劣化などの火災保険の注意点について解説します。
(1)経年劣化による損害は対象外
経年劣化はお支払いの対象にならない
申請した損害が対象外となるケースの一例として「経年劣化」があります。どんな建築物でも時間の経過と共に劣化が進みます。
時間の経過とともに外壁塗装が色褪せたり、シーリングが痩せたりひび割れたりします。プラスチックの雨樋が太陽熱でゆがんだり、木部に打たれた釘が飛び出てきたりするのも経年劣化の一例です。屋根のスレートも経年劣化でひび割れが発生することがあります。
こうした経年劣化は、自然災害などの保険で対象とする事故によって生じた損害ではなく、火災保険では対象外と規定されているため注意が必要です。
(2)お支払いする保険金と修理見積金額との差について
火災保険は損害のすべてをカバーするものではない
経年劣化は見えないところでも進んでいます。例えば、瓦は下地となる板(野地板と言います)に固定されていますが、強風で瓦が飛んでしまった場合、修理業者は瓦を葺き直すと同時に下地が劣化していれば下地の補修も行います。当然、見積書には下地の補修費用が含まれています。弱っている下地をそのままにして瓦だけ直しても、また風で飛んでしまうリスクがあるからです。
しかし、火災保険では、経年によって弱ってしまっている部分は経年劣化と判断されます。このため、この場合の下地をどこまで確認対象とするかは現地調査の結果によることになります。
契約者が注意すべきは、たとえ風災による損害と認定されても、火災保険は修理に必要な金額のすべてをカバーするものではないという点です。お支払いされる保険金と修理業者の見積金額が必ずしも一致するとは限りません。
(3)不明点は保険会社に質問するのがベスト
保険会社や代理店はあなたの強い味方
火災保険の申請や認定内容について分からないことや質問がある場合は、保険会社の窓口や代理店に相談するのがベストです。あなたの立場に寄り添い、申請や確認がスムーズに進むよう力を尽くしてくれます。
まとめ
大規模な自然災害が増え、以前よりも身近に感じる機会が増えてきた火災保険。あなたの大切な財産を守ってくれる保険なのですから、人任せにしないで火災保険について理解する意識を持ち、保険を上手に活用することを心がけましょう。
そして、火災保険の請求(申請)手続きは決して難しいものではありません。どのように対応すればいいか分からない場合は、保険会社や代理店に相談することが解決への第一歩になるはずです。
関連商品・サービス
関連記事
- 保険金の請求と支払い 保険の基礎知識損害保険


