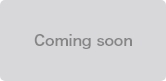インド
インドは、世界にあるマングローブ林の約2.8%の面積を保有していましたが、沿岸開発や一部劣化によって失われています。このプロジェクトでは、天然のマングローブ林が存在しなかったインド西部・グジャラート州の河口で植林活動を行っています。
マングローブ植林活動レポート
植林したマングローブの様子
インドでは、2009年からNGO「国際マングローブ生態系協会(ISME)」が、現地NGO「Daheda Sangh」とともに、インドマングローブ協会の協力を得ながら、ヴァドガム村の住民のみなさんとともに植林事業を進めています。多くの住民が農業で生計を立てているこの地域で、マングローブ植林を実施する目的は、「農地に浸入する海水を軽減すること」、「波を弱めて海岸が削られるのを防ぐこと」、「乾季に家畜への飼料を供給すること」などです。
- 2024年度の植林面積 60ヘクタール
- 累積植林面積 1,185ヘクタール
マングローブ植林活動状況
2024年度は、サバルマティ川河口付近のヴァドガム村やヴァンアージ村、これまでの植林地にも近い植林地60ヘクタールに、ヒルギダマシの種をまきました。
ヒルギダマシの種は、流されてしまうことを考慮して、原則1ヶ所に3つずつの種をまいています。ヒルギダマシの種の表面は細かな毛で覆われており、水をはじきます。そのため水中では浮いてしまい、潮の干満でまいた種が流れてしまう可能性があります。この問題を防ぐために、種をまく前に表面の皮をむく作業を行っています。
植林活動にあたっては、SDGsの目標5である「ジェンダー平等を実現しよう」の実現を目指して、女性の雇用を増やす努力をしています。

まく前に、ヒルギダマシの種の皮をむいている様子ⒸISME

種をまいて約1週間で発芽したマングローブⒸISME

多くの女性が、植林活動に参加しましたⒸISME
植林地の様子
これまでの現地調査では、洪水の際に土壌が80cm以上も堆積することが珍しくありませんでした。その主な理由は、ヒルギダマシが生い茂ることで根や幹が水の流れを弱め、河川の流れが遅くなるためです。その結果、上流から運ばれてきた土壌の粒子が水中にとどまらず、土壌の堆積が進むのです。このように、ヒルギダマシの植林によって土壌の堆積が促進され、陸地が増えたこと、そして農地への高波の被害を防ぐことができていることは、マングローブを植える大きな利点の一つです。

まいた種が5~6カ月で苗に育ちましたⒸISME

2011~2012年に植えたヒルギダマシが土壌の堆積を促進しましたⒸISME

マングローブを植えたエリアで確認できたフラミンゴの群れⒸISME
今後の活動予定
次年度は、植林面積の実測や適期での採種などの植林活動を行います。