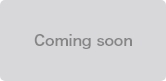ミャンマー
ミャンマー中南部イラワジ管区の天然のマングローブ林は、1992年に炭焼きが禁止されるまで、炭生産のために伐採されたり、米の増産政策により天然のマングローブ湿地が水田に転換されたりしてきました。しかし、1994年に植林した者に30年間の森林利用権を与える「社会林業条例(Community Forestry Instruction)」が制定され、今では民間による植林が推進されています。
マングローブ植林活動レポート
植林したマングローブの様子
ミャンマーでは、1999年よりNGO「マングローブ植林行動計画(アクトマン)」が、FREDA(ミャンマー森林資源環境開発協会)の協力を得て、FUG(Forest Users Group)という住民による森林利用グループが中心となり、活動を進めています。炭や米の生産のために荒廃した天然のマングローブ林を環境保全森林省森林局の住民参加型の社会林業(Community Forestry)手法により、修復再生することを目的としています。
- 2024年度の植林面積 100ヘクタール
- 累積植林面積 3,239ヘクタール
マングローブ植林活動状況
2024年度は、これまで25年間活動してきた植林地から、イラワジデルタ西部にあるイラワジ管区ラプタ市のチャーカンクウィンパウ森林保護区へ移動しました。そして、ティッポンコン村、ダヤピュージー村、ミャヤゴン村という3カ所で、合計100ヘクタールの植林活動を行いました。
植えたマングローブは、マルバヒルギダマシとオヒルギ、ロッカクヒルギの3種類で、合計30万2,500本です。植林作業には、地元の43家族が参加しました。また、苗木は前期事業地であるイラワジデルタ南東部のピンダイェ森林区にあるオッポクウィンチャン村とタンジータン村から、片道9時間ほどかけて、木造船で運搬しました。

ミャヤゴン村で順調に育つマングローブ

ダヤピュージー村でマングローブを植えている様子

マングローブの苗木を木造船に積み込んで、植林地まで運搬している様子
植林地の様子
2024年度に植林したマングローブの2024年12月時点の各植林地の活着率は順調で、3カ所のマングローブの活着率は平均約91%と高く、多くのマングローブが成長を続けています。
また、次年度用の苗木づくりも始めており、今年度と同様にマルバヒルギダマシとロッカクヒルギ、オヒルギの苗木を育てています。

ミャヤゴン村で植えたマングローブの生存率を調査している様子

マルバヒルギダマシの苗床に種をまく様子

カカレイ村で、次年度の植林予定地の調査をしている様子
今後の活動予定
次年度は、今年度の植林地、イラワジ管区ラプタ市のチャーカンクウィンパウ森林区から、少し東にあるピンアラン森林保護区に事業地を移して、6つの村の合計100ヘクタールの植林地で活動を行う予定です。