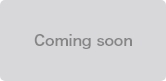アマモ場の現状
アマモ場の減少
高度成長期に藻場(アマモなどの海草藻場、ワカメなどの海藻藻場)は大幅に減少しました。減少の原因としては「沿岸域の開発・埋め立て」、「海水の透明度低下」、「陸域からの排水負荷の増加による水質の変化」などが挙げられます。
1993年に制定された環境基本法などの法令や、市民レベルでの自然環境保全意識が高まったことから、全国各地で藻場の造成活動が進んでいますが、近年では再び「磯焼け」による藻場の消失が、全国各地で確認されています。



磯焼けの原因
磯焼けとは、藻場からアマモ(海草)やワカメ(海藻)などが消失してしまった状態を言い、海底が焼け野原のように見えることから、このように呼ばれています。
様々な原因があると考えられていますが、水産庁の「第3版
磯焼け対策ガイドライン」では、「食害」「枯れる/芽生えなくなる」「流失する」のいずれか、もしくはこれらの組み合わせによるものとされており、全国的に磯焼けが広がっている背景には、温暖化の影響が大きいと言われています。
-
・食害
海草や海藻を魚やウニが食べてしまうことを食害といいます。海水温の上昇によって、南方系の植食魚が北上してきたり、海草や海藻が繁茂する冬の時期にも高水温によって魚やウニの活動が停滞しないことなどから、食害にあう海草や海藻が増加しています。 -
・枯れる/芽生えなくなる
水温が高すぎたり、塩分が低すぎたりする状態が続いた場合、海草や海藻が枯れてしまいます。また、岩場の海藻場に堆積物が積もることで、新たな遊走子の着生が妨げられ、新芽が生えなくなったり、成長が妨げられたりします。なお、堆積物の増加は、気候変動による暴風雨の激化や降水量の増加によって引き起こされることもあります。 -
・流失する
台風などにより暴風雨が激しくなると、波が強くなり、海の中がかく乱され、その影響でアマモ(海草)やワカメ(海藻)が流されやすくなります。温暖化により大型の台風は増えています。
このように、近年の温暖化は藻場の減少の大きな要因となっています。
藻場が減少すると、生き物の生息場所や産卵場所も減少し、それに伴ってそうした場を生活の一部として利用している生き物も減少してしまいます。また、海をきれいにする力も失われてしまいます。