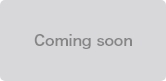タイ
タイでは、第2次世界大戦後、スズの採掘、エビの養殖場や船着場の造成、炭作りなどの開発により天然のマングローブ林が伐採されてきましたが、ラノーン県ではこれまでの植林活動により大きなマングローブ林が広がっています。
マングローブ植林活動レポート
植林したマングローブの様子
タイでは、1999年よりNGO「オイスカ」がラノーン県のマングローブ資源開発局の協力を得て、地元住民のみなさんの参加に重点を置いたマングローブの植林活動を実施しています。住民のみなさんはマングローブ林についての理解を深め、その大切さを実感し、多くの人が自主的に植林、補植の活動に参加するようになってきました。今後は保全活動の一環として、植林地のマングローブの種類や樹高、生物多様性などについて調査することにも力を入れていくことにしています。
- 2024年度の植林面積 6ヘクタール
- 累積植林面積 1,164ヘクタール
マングローブ植林活動状況
2024年9月に、東京海上グループの社員等による植林を実施しました。国内外から26名のボランティアが参加し、植林を行いました。

住民グループによる植林地の準備作業の様子

東京海上グループ社員のボランティア活動。日本からの参加者のほか8カ国26名のボランティアが参加しました

2024年9月に植えたマングローブの様子
植林地の様子
20年以上継続してきた森づくりをベースに、住民たちは森を活かした安定した生活を目指しています。海岸地域では、豊かなマングローブ林のおかげで災害から守られ、地域の安全性が向上しています。また、ラノーン県の生物保護圏の中に植林地があるのですが、この生物保護圏を支えるという意味でも、マングローブ林は重要な役割を果たしています。
さらに、マングローブ石けん、お茶、薬や虫よけ、草木染などの商品づくりのほか、水産物加工や小物づくりなどが、さまざまな場所で注目され始めています。中でも、ンガオ村の女性グループによるマングローブ製品作りが、タイの有名インフルエンサーの訪問を受けて注文が殺到したり、100人規模の大グループによる視察が行われたりと、人気が高まっています。
地域住民がマングローブの知識を得る機会にもなっていて、環境と共存した地域開発、女性の活躍の場のモデルケースとして他県にも注目されています。日本の大学生がラノーン県の森づくりと地域開発の現場を訪れて、漁村にホームステイをするなどの取り組みも行われました。

過去の植林地で下草を刈っている様子

2020年の植林地で5メートルほどに成長したマングローブ

漁師がカニ漁を行っている様子
今後の活動予定
次年度は、新たな植林地の準備と、マングローブの植林活動を実施する予定です。